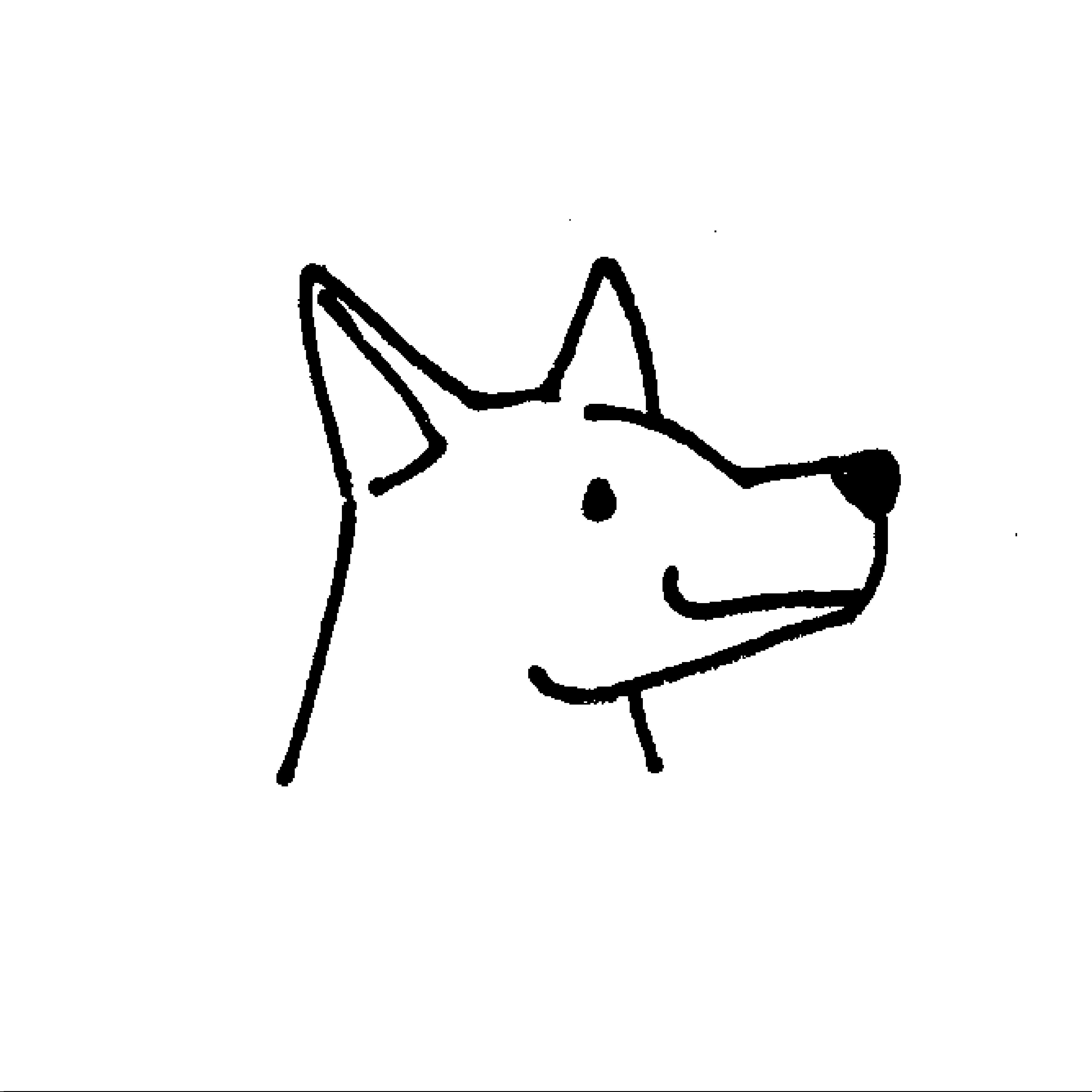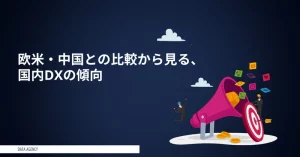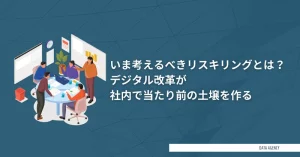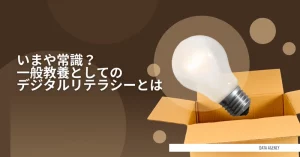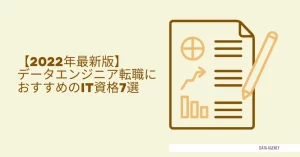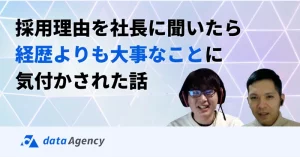海外と比較した日本のデジタル教育
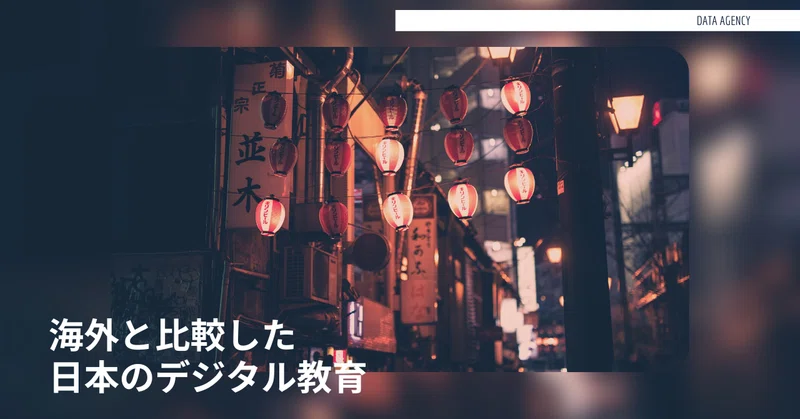
私たちの生活に急速に浸透したデジタル技術。現代では生活の必需品としてとらえられるようになり、学校でも情報科目を学ぶようになりました。今日は、EU・中国・アメリカが日本と比較してどのようにデジタル教育を進めているのかを紹介します。
EU全体でデジタル教育の恩恵を目指すヨーロッパ
EUは、個々の国というよりも全体での成長を目指しているのが大きな特徴です。そのため、EU圏や地球環境を考え、環境保全やSDGsにも力を入れています。2025年までに年齢に関係なく、全ての欧州人がデジタル教育の恩恵を受けられる「European Education Area」を実現することを目標にしています。
EU内では国によって異なる言語が使われているため、多言語教育の充実とデジタル教育は同等の重要度で考えられています。
2018年に公開された「Digital Education Action Plan」では、大きく次の2点が優先事項として挙げられています。
- 教育および学習のためにデジタル技術をよりよく活用する
- DXのための適切なデジタルスキルとコンピテンシーの開発
| EU | 日本 | |
|---|---|---|
| デジタル教育の対象 | ・すべての欧州人 ・COVID-19の影響で職を失った人が新しいスキルを得るため |
・高校生を中心に実務に近い学び ・小学生には、デジタルリテラシーを中心とした学び |
| 教育現場でのICT活用 | ・ヨーロッパ全体で学校と教師をネットワーク化(*1) ・無料のウェビナーやオンラインコースでの専門的な能力開発コース |
・病気療養中の生徒への学習手段(*2) ・ICT設備だけでなく、LAN回線、教室の冷暖房導入など環境整備を整えられていない |
*1,*2 出典:Annual Report 2020 European Schoolnet
令和3年度 高等学校段階の病気療養中等の生徒に対するICTを活用した遠隔教育の調査 研究事業 中間報告会
子どもの教育資金は惜しまない中国
地域によって環境や生活レベルが全く異なる中国。しかしながら、多くの家庭では子どもの教育資金は惜しまない、全体的に教育熱心な国と言えるでしょう。また、デジタル教育はSTEM教育の一環として捉えられ、近年カリキュラムが充実しています。
このような背景と人口の多さから成る巨大市場を狙って、国内外から教育現場への進出企業が多く、競争が激化しています。
| 中国 | 日本 | |
|---|---|---|
| デジタル教育の対象 | ・2017年に情報教育の開始を1年生から行うことを策定。(*3)AI教育も推進。 | ・高校生を中心に、より実務に近いレベルの学びが増えている ・小学生には、デジタルリテラシーを中心とした学びを提供 |
| 教育現場でのICT活用 | ・早期教育、語学、企業eラーニングなど、オンライン教育が盛ん ・学校におけるICT環境整備において、資金面での課題がある |
・病気療養中の生徒への学習手段としても考えられている ・ICT設備だけでなく、LAN回線、教室の冷暖房導入など環境整備を整えられていない |
*3 出典:中国が行っているプログラミング教育とは?国としても急成長!親の教育熱がスゴイ
教育の場でも自由度が高いが、その分格差も大きいアメリカ
いわゆる飛び級やホームスクール、大学での複数学部履修や学び直しなど、教育制度でも自由度の高いアメリカ。
そして、入学は簡単だが卒業が難しいといわれるのがアメリカの大学。1科目の勉強時間は1日2~3時間必要といわれます。また、公立4年制大学の平均の学費(*4)は州内居住者でも$21,370、州外居住者だと$31,730と驚くほどの高額です。学業の厳しさと学費の高さからか、4年制大学で1学期目に18.4%がドロップアウトした(*5)という数字もあるほどです。
学習意欲が高い人は学びを深めることができますが、その反面、比較的簡単に学習をやめる人も多く存在します。
| アメリカ | 日本 | |
|---|---|---|
| デジタル教育の対象 | ・code.orgという非営利団体がコンピュータサイエンスのカリキュラムを提供。4歳からのプログラムもある ・全米で見てみるとコンピュータサイエンスの授業が行われている公立高校は51%と意外に少ない。 ・カレッジを通してGoogle Certificate Programの無料受講など、企業と大学の提携も(*6) |
・小学校から 情報活用能力の育成 プログラミング教育 などが推進されている ・高校で情報科目が必修になった |
| 教育データの利活用 | ・各学校のスコアやランキングが公表され、高スコアの学校に通うために引越しをする人もいる | ・教育データの利活用の原則に従って安心・安全な仕組みを目指している(*7) ・学年や学校のデータというよりつ個々の生徒や特定の状況に活用しようとしている |
| 教育現場でのICT活用 | ・コロナ前からeラーニング、オンラインクラスなどが学校現場で活用されていた | ・病気療養中の生徒への学習手段としても考えられている ・ICT設備だけでなく、LAN回線、教室の冷暖房導入など環境整備を整えられていない |
*4 出典:How Much Does it Cost to Study in the US?
*5 出典:College Dropout Rates
*6 出典:Google makes career certificates free for US community colleges
*7 出典:教育データの利活用に係る論点整理(中間まとめ)概要
まとめ
日本でも取り組もうとしている多言語教育やSTEM教育などが海外でも行われていることがわかりました。また、デジタル人材の育成は急務であることから、海外でも大人のリスキリングにも力を入れていることが見えてきました。日本でも終身雇用制度の崩壊で、定年に関係なく長く働くことも想定される中、海外の教育事情についても大変参考になるでしょう。
さらに官民連携した教育の取り組みは、日本リスキリングコンソーシアムの発足など日本でも始まっています。このような動向を見ながら、できることから学習を始めるとよいでしょう。